画像:新しい”Steamハードウェアファミリー”
Steam Deckの“次”は、一つではなかった
Valveが日本時間2025年11月、3つの全く新しいハードウェアを電撃的に発表した 。PCゲーム市場に衝撃を与えた「Steam Deck」の“次”を待ち望んでいた多くのゲーマーにとって、その答えは予想を遥かに超えるものだった。
発表されたのは、以下の三位一体である。
- SteamFrame: 長らく「Deckard」のコードネームで噂されてきた、新型ワイヤレスVRヘッドセット 。
- Steam Machine: リビングルームでのPCゲーム体験を再定義する、ハイパワーな据え置き型コンソール
- Steam Controller: Steam Deckの高度な操作性を備えた、新世代のゲームコントローラー
これらは個別の製品でありながら、「ファミリー・オブ・デバイス(a family of devices)」として、シームレスに連携するエコシステムを構成する 。
本記事では、この衝撃的な発表の「全貌」を、Valveが描く「PCゲームの未来」という戦略的意図まで踏み込み、最速で詳報する。
全体像:Valveが仕掛ける「三位一体」のエコシステム戦略
今回の発表は、Steam Deckの成功と、かつての失敗から得た教訓の集大成である。
Steam Deckの成功と、2013年「Steam Machine」の失敗
2013年に発表された初代「Steam Machine」構想は、野心的であったものの、結果として失敗に終わった 。その最大の敗因は、WindowsゲームをLinuxベースのSteamOSで実行するための互換レイヤー「Proton」が未成熟であったこと、そしてハードウェア製造をサードパーティに依存した結果、製品の体験が統一されなかったことにある 。
しかし2022年、Valveは「Steam Deck」でこの雪辱を果たした。成熟したProton 、Valve自らが最適化したハードウェア、そして「PCゲームライブラリを持ち運ぶ」という明確なコンセプトが組み合わさり、世界的な成功を収めた 。
この成功は、Valveに2つの明確な「次の課題」を提示した。
- リビングルームでの体験不足: Steam Deckをテレビにドック接続しても、その高度な入力(トラックパッド、背面ボタン)をリビングで快適に操作できる純正コントローラーが存在しなかった
- パフォーマンスの限界: Deckはあくまで携帯機であり、リビングの大画面で高解像度・高フレームレートのゲームを動かすには明らかな力不足があった
2026年に発売が予定される この3つの新製品は、これら2つの課題を完璧に解決するために設計されている。
Steam Machineは、Steam Deckの「6倍以上」 のパワーでリビングルームのパフォーマンス不足を解決する。Steam Controllerは、Steam Deckの操作性 をリビングルームに持ち込む。SteamFrameは、そのSteamエコシステム全体を、新たにVRという空間へ拡張する 。
これは、既存のDeckユーザーに対する強力なアップセル戦略であると同時に、新規ユーザーをSteamエコシステムに引き込むための、新たな3つの入り口となる。
【SteamFrame】:”ストリーミングファースト”のスタンドアロンVR

最も注目を集めているのが、新型VRヘッドセット「SteamFrame」である。
「Index 2」ではない、Valveの新たな回答
まず明確にすべきは、本機が「Valve Index 2」とは呼ばれていない点である 。高価なPCが必須だったIndexとは異なり、SteamFrameは2つの側面を持つハイブリッドデバイスである。
1. スタンドアロン性能
本機はQualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650) プロセッサを搭載 し、ARM版のSteamOSをネイティブで実行する 。これにより、「Fex」と呼ばれるx86-ARM変換レイヤー(トランスレーションレイヤー)を介して 、『Hades II』のようなフラットスクリーンゲームや、一部の軽量なPC VRゲームをPCなしで単体実行できる 。Steamストアでは、Deck Verifiedと同様の「Frame Verified」バッジが導入される 。
2. ストリーミング性能
しかし、Valve自身は本機を「ストリーミングファースト」のヘッドセットと呼称している 。本機の真価は、同梱される専用の6GHzドングル にある。これにより、ゲーミングPCや新型Steam Machine から、高忠実度(ハイフィデリティ)なPCVRゲームを、低遅延かつ高品質なワイヤレスストリーミングでプレイできる。
この戦略は、スタンドアロン性能を優先するMeta Questとは明確に異なる。Valveは、自社の強みである数千万人の既存PCゲーマーと、膨大なSteamライブラリを最大限に活かすため、「高品質なPCVR体験」をワイヤレス化することを最優先に据えた。
その核となる技術が、アイトラッキング を利用した「Foveated Streaming(中心窩ストリーミング)」である 。これは、ユーザーの視線が向いている中心部だけを高解像度でストリーミングし、周辺部の解像度を落とすことで、ワイヤレス接続ながら劇的な帯域幅の節約と品質向上を両立させる技術だ。
誤解厳禁:「空間的ゲーム(Spatial Gaming)」とモノクロ・パススルー
Apple Vision Proが提唱する「空間コンピューティング」 や、Meta Quest 3のフルカラーMR(複合現実)を期待しているユーザーは注意が必要である。
SteamFrameのパススルー(現実世界を視認する機能)は、モノクロである 。
これは技術的妥協ではなく、「ゲーマーファースト」の思想に基づく戦略的な選択である。フルカラーMRはデバイスのコスト、重量、消費電力を跳ね上げる。Valveは、高価な「万能MRデバイス」を目指すのではなく、ゲーマーに必要な「VR体験の質」にリソースを全集中させた 。
このモノクロ・パススルーは、MRでゲームを遊ぶためのものではなく、VR体験中に飲み物を取ったり、キーボードの位置を確認したりするための「ユーティリティ機能」として割り切られている 。赤外線イルミネーターにより、暗闇でも視認できるという利点もある 。
この割り切りにより、SteamFrameは総重量435g と、Quest 3 よりも軽量な設計を実現している。「Steam Frame」という名称も、MR空間ではなく、SteamVRのオーバーレイ機能の新名称「Frames」(VR空間内で複数のフラットゲームやアプリを扱う機能)に由来する可能性が高い。
なお、ヘッドセット前面には拡張スロットが用意されており、将来的にはサードパーティ製のカラーパススルーMODなどが登場する可能性も示唆されている 。
【SteamFrame 主要スペック】
| 項目 | スペック |
|---|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650) |
| OS | SteamOS (on ARM) |
| 解像度 | 2160 x 2160 (片目) |
| リフレッシュレート | 72-120Hz (144Hz実験的) |
| レンズ | パンケーキレンズ |
| 視野角(FOV) | 最大110度 |
| 重量 | 435g (コア部190g) |
| トラッキング | インサイドアウト (4カメラ) |
| パススルー | モノクロ(赤外線) |
| アイトラッキング | 搭載 (中心窩レンダリング/ストリーミング用) |
| RAM | 16 GB |
| ストレージ | 256 GB / 1 TB (MicroSDスロットあり) |
| 接続 | 専用6GHzドングル (PCVRストリーミング用) |
| 発売日 | 2026年早期 |
| 価格 | TBC (未定) |
このスペックは、一般的なゲーマーには朗報である一方、既存のコアなVRユーザー層、特に『VRChat』などで全身の動きをトラッキングする「フルトラ(フルボディトラッキング)」を常用するユーザーからは、懸念と期待が入り混じった目で見られている。
懸念点:ベースステーション方式の廃止 最大の懸念は、Valve Indexが採用していた高精度な「ベースステーション(Lighthouse)トラッキング」を廃し、「インサイドアウト方式」 のみを採用した点である。
VRChatterが使用する「Viveトラッカー」といったフルトラ機器は、ベースステーションによるトラッキングを前提としたものが多く、依然としてフルトラ用途では最も高精度とされている。一部のコアユーザーからは「ベースステーション非対応なら購入しない」 という厳しい声も上がっている。
期待点①:高精度アイトラッキング 一方で、VRChatterにとって最大の朗報は「アイトラッキング(視線追跡)」 の搭載である。これが「ソーシャルゲームでの使用」 と明記されている通り、VR空間内での自然なアイコンタクトや表情の伝達が可能になり、ソーシャルVR体験を劇的に向上させる可能性がある。
期待点②:「真に低遅延な」ワイヤレス体験 もう一つの期待は、ワイヤレス性能である。「ストリーミングファースト」 という思想自体は、PCVRのコアユーザーにとって目新しくない。しかし、多くのユーザーが既存のWi-Fi 6環境ですら満足な低遅延体験を得られていないのが実情である。
SteamFrameが採用する専用の6GHzドングルと、視線を利用した「Foveated Streaming」 が、ついに『Beat Saber』 のような高精度・低遅延が要求されるゲームでも有線と遜色ない体験を提供できるか、その真価が問われている。
結論として、SteamFrameはフルトラという「ニッチだが重要なコア体験」 を切り捨てる(あるいはサードパーティのMODに委ねる)代わりに、利便性の高いインサイドアウト方式と、次世代のソーシャル体験(アイトラッキング)、そして高品質なワイヤレス体験をトレードオフとして提示したデバイスであると言える。
【Steam Machine】:”Deckの6倍速”、リビング制圧コンソール

次に発表された「Steam Machine」は、2013年の構想を、Steam Deckの成功体験を経て「Valve純正コンソール」として昇華させたものだ。
2013年の「失敗」を乗り越えた、Valve純正コンソール
これは「Steam Deck 2」ではなく、「据え置き型Steam Deck Pro」と呼ぶべきデバイスである。
その性能は「Steam Deckの6倍以上」とされており、リビングルームの大画面テレビでのゲーム体験を主眼に置いている。CPUにはAMD Zen 4 (6コア)、GPUにはSemi-custom AMD RDNA 3 (28 CU) を搭載。これはGPU単体でRX 7600Mに匹敵する性能とされ、FSR(アップスケーリング技術)を利用した4K/60fpsでのゲームプレイや、レイ・トレーシングにも対応する。
本機はゲーミングPCと競合するものではない。むしろ、「ゲーミングPCは複雑で面倒だが、PS5やXboxの閉じたエコシステムには不満」という、最も広大なコンソールゲーマー層をSteamに引き込むための戦略的製品である。
SteamOSとProtonの成熟により、PCゲーム特有の複雑さを排除。「高速サスペンド/レジューム」機能など、コンソール並みの手軽さで、Steamの膨大なライブラリと安価なセールという最大の武器を提供する。
デザインは、リビングの棚に収まるよう設計されたコンパクトな黒い立方体で、まさにValveが2013年に夢見た「リビングルームの制圧」を、今度こそ実現するための“本命”デバイスと言える。
【Steam Machine 主要スペック】
| 項目 | スペック |
| CPU | AMD Zen 4 (6コア/12スレッド) |
| GPU | Semi-custom AMD RDNA 3 (28 CU) |
| VRAM | 8 GB GDDR6 |
| RAM | 16 GB |
| ストレージ | 512 GB / 2 TB NVMe SSD |
| 拡張 | microSDカードスロット |
| 前面 I/O | 2x USB 3.0 Type-A |
| 背面 I/O | 2x USB 2.0 Type-A, 1x USB-C (10Gbps), DP 1.4, HDMI 2.0, Ethernet (1Gbps) |
| ワイヤレス | Wi-Fi 6E, Bluetooth, 内蔵Steam Controllerレシーバー |
| OS | SteamOS |
| 発売日 | 2026年早期 |
| 価格 | TBC (未定) |
【Steam Controller】:“ドリフト耐性”と“Deckの操作性”の融合
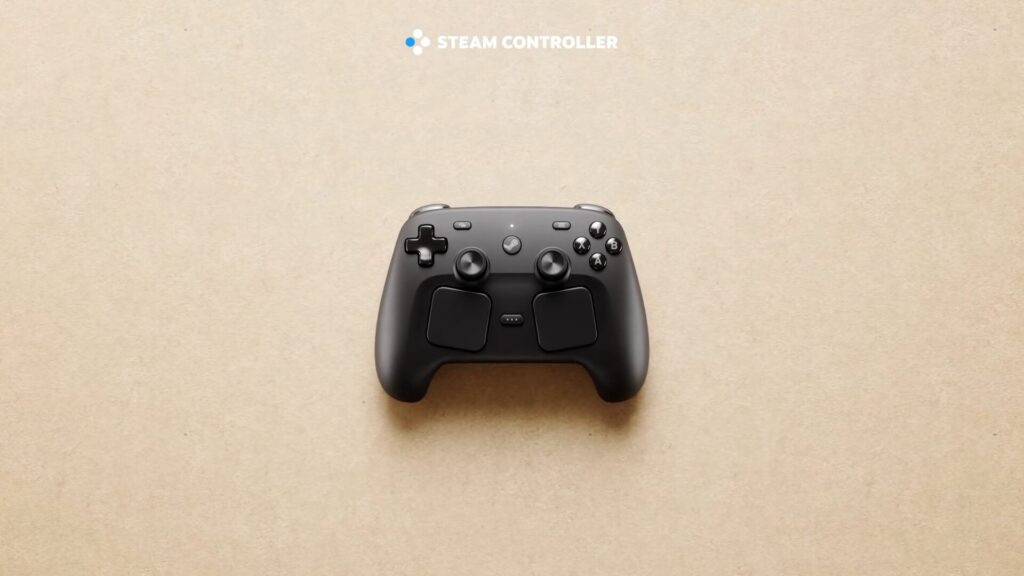
エコシステムの最後のピースを埋めるのが、2019年に生産を終了した初代モデルを大幅に進化させた、新型「Steam Controller」である。
このコントローラーは、前述の「Steam Deckをドック接続した際の入力不足」という課題を直接的に解決するために設計された。
そのデザインは「Steam Deckからスクリーンを取り外したもの」と評するのが最も正確だろう。Steam Deckの強みであった2つの高精度トラックパッド、ジャイロ、そして4つの背面グリップボタンを、スタンドアロンのコントローラーとして完全に再現している。初代と異なり、サムスティックも左右両方に搭載された。
しかし、本機の最大の注目点は、トラックパッドではなく「サムスティック」にある。
このスティックには「TMR(トンネル磁気抵抗)」技術が採用されており、物理的な接触に依存しないことで、原理的にスティックドリフト(経年劣化でスティックが勝手に動く現象)への耐性(stick-drift resistant)を持つ。
これは、任天堂のJoy-ConやソニーのDualSenseなど、現代の主要なコントローラーが抱える最大の不満点に対する、Valveからの明確な「技術的回答」である。
このコントローラーの登場により、「Steam Deck」、「Steam Machine」(内蔵レシーバー搭載)、「SteamFrame」(VR内でのフラットゲーム操作)という、Valveのすべてのハードウェアにおいて、トラックパッドと背面ボタンを含む「Steam Input」という高度な操作性が標準化されることになる。
35時間以上のバッテリー寿命に加え、Bluetooth、有線(USB-C)、そして最大4台まで低遅延接続できる専用2.4GHz「パック」(充電器兼用)に対応し、PCゲーマーにとっての「決定版」コントローラーとなる可能性を秘めている。
価格と発売日、そして次世代ゲーム戦争への影響
2026年、PCゲームの「標準」が変わる
今回発表された「SteamFrame」「Steam Machine」「Steam Controller」の3製品は、すべて「2026年早期」の発売が予定されている。販売地域はSteam Deckと同様(日本を含む)となる見込みだ。
しかし、価格は3製品すべてTBC(未定)とされた。
2025年後半のホリデーシーズンを前に、あえて価格を発表せずに「2026年早期」の発売を予告したValveの戦略は明確である。
これは、Metaの新型Questや、ソニー、任天堂の次世代機を(ホリデーに)購入しようと検討している潜在顧客に対し、「待て」という強力な牽制(けんせい)球を投げたに等しい。
Valveは、競合他社が2026年向けの価格設定をすべて提示した後、市場の「最後出しジャンケン」で、最も戦略的な価格を提示することができる。Steamという強力なソフトウェア収益基盤を持つValveは、ハードウェアの利益率を(あるいは赤字を)許容してでも、市場シェアを獲るための「戦略的価格」を設定することが可能である。
Steam Deckという「一点突破」の成功から、VR・リビングルーム・入力デバイスという「面」での制圧へと、Valveの戦略は大きくシフトした。
2026年、我々のゲーム環境の「標準」は、この三位一体によって塗り替えられることになるのか。その運命を分ける「価格」の発表が、今から待たれる。



